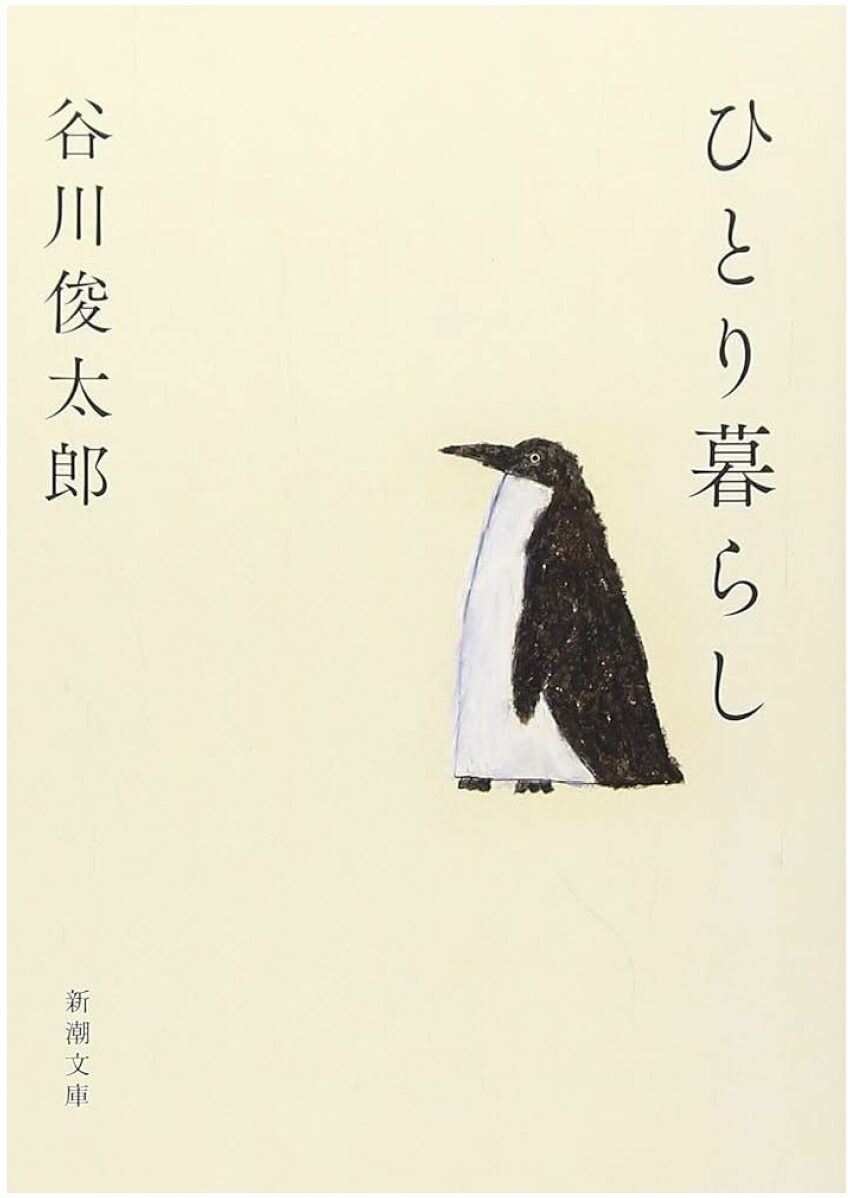
そのことばのもとに、いかに人をして立ち止まらせるか。詩のいのちはその地点に存していると思う。
じっさい、わたしたちもまた、なんどかそうした詩のまえに立ち止まり、ことばの綾なす神秘に触れ、青く透明な深淵をのぞき込むようにして、自らのそれぞれの人生を見つめてきたのだと思う。
谷川俊太郎の詩業は長い。そしてその詩業には、どこかおだやかな光条をたたえている。
二〇歳のころ、朝鮮動乱が勃発した年、鉛筆で書いた「ネロ」を三好達治の推薦で『文学界』に発表し、それを含む第一詩集『二十億光年の孤独』(1952年)を世に出してから、2024年11月に92歳で死去するまで、谷川俊太郎は、多くの詩を編んできた。
・・・万有引力とはひき合う孤独の力である
(『二十億光年の孤独』)
カムチャツカの若者が きりんの夢を見ているとき
メキシコの娘は 朝もやの中でバスを待っている
ニューヨークの少女が ほほえみながら寝がえりをうつとき
ローマの少年は 柱頭を染める朝陽にウインクする
この地球では どこかで朝がはじまっている
ぼくらは朝をリレーするのだ 経度から経度へ
そうしていわば交替で地球を守る
眠る前のひととき耳をすますと どこか遠くで目覚まし時計のベルが鳴っている
それはあなたが送った朝を だれかがしっかりと受けとめた証拠なのだ
(「朝のリレー」『谷川俊太郎詩集』河出書房版)
生きているということ いまを生きているということ
それはのどがかわくということ 木もれ陽がまぶしいということ
ふっと或るメロディを想い出すということ
くしゃみをすること あなたと手をつなぐこと
(「生きる」『うつむく青年』)
これが一番いいもの
この短い単純きわまりない旋律が ぼくの息をこらす ぼくはそっと息をはく
人を愛することの出来ぬ者もモーツァルトに涙する
もしそれが幻ならこの世のすべては夢にすぎない
(「人を愛することの出来ぬ者」『モーツァルトを聴く人』)
どんなよろこびのふかいうみにも
ひとつぶのなみだが とけていないということはない
(「黄金の魚」『クレーの絵本』)
苦しみという名で 呼ぶことすらできぬ苦しみが
あなたの皮膚から内臓へ 内臓からこころへ
こころから私が決して 行き着くことのできぬ深みへと
歴史を貫いていまも疼きつづける
・・・中略・・・
その日私はそこにいなかった
私はただ信じるしかない 怒りと痛みと悲しみの土壌にも
喜びは芽生えると 死によってさえ癒やされぬ傷も
いのちを滅ぼすことはないと
その日はいつまでも 今日でありつづけていると
(「その日― August 6」『シャガールと木の葉』)
道ばたのこのスミレが今日咲くまでに
どれだけの時が必要だったことだろう
この形この色この香りは計りしれぬ過去から来た
遠く地平へと続くこの道ができるまでに
どれだけのけものが人々が通ったことだろう
足元の土に無数の生と死が埋もれている
・・・中略・・・
未だ来ないものを人は待ちながら創っていく
誰もきみに未来をおくることはできない
何故ならきみが未来だから
(「未来へ」『すき』)
さよならは仮のことば 思い出よりも記憶よりも深く
ぼくらをむすんでいるものがある
それを探さなくてもいい信じさえすれば
(「さよならは仮のことば」『私』)
谷川の詩のアンソロジーである『さよならは仮のことば』にある詩を、上記のようにざっとあげてみても、漢語の少ない平易なことばが織りなす光の粒々が、砂金のように浮き出てくる。それはまた、永遠の少年が宿している光芒のようにも見える。
谷川俊太郎は、東京・杉並の成田東に住んでいた。学生だったわたしの住んでいたアパートもその近くにあり、彼の父君である哲学者の谷川徹三氏の姿を、わたしはよく地下鉄南阿佐ヶ谷駅そばの「書源」という書店で見かけた。
「書源」は、通常の書店がおいていないような哲学書や思想書など硬派の本がたくさん置いてあり、常連さんは、その書棚を時間をかけて眺めるのだが、そのなかに谷川徹三氏もいた。だが、その「書源」も、書店文化の衰退からか、数年前に閉店した。
京都帝大哲学科出身のインテリであり、かつて法政大学総長であった父君は、ハイカラでりゅうとした身なりで、見るからに帝大アカデミズムを地でゆく人の余裕めいたものを身につけていた。いっぽう、その子息であった詩人は、あのころすでに四〇歳半ばを超えていたのだろうか、父君とくらべ、どちらかと言えばきゃしゃな印象だった。
じつはわたしの出身地である北東北からは、中央では無名であるが、多くの詩人が出ている。その詩人たちは、北国の風雪に対峙して風土と抒情を切り結ばんばかりの激しい詩魂と風貌をもつ人が多かった。そこに酒が入ると血は滾り、それは一層激しいものとなった。それを見るにつけ、詩を書くということは、けっしてたおやかな振る舞いではない。高校生だったころ、わたしは、そんなふうに思っていた。
しかし、アパートの近くで出会ったかの詩人は、穏やかな感じの人だった。それは、ひどく都会的に見えたし、ドクドクとした血の気からは遠い印象だった。
ところで、谷川俊太郎は大学に行っていない。年譜等を見ても、その理由はわからない。下世話なことではあるが、父は京都帝大卒の哲学者。母は政友会に属する衆議院議員の娘。ひとりっ子として育った詩人の家庭環境を考えれば、それなりの大学に進学してもおかしくなかったはずである。
だが、高校生のころひどく成績が下降し、しかもたびたび教師と対立したとのことで、定時制に転学し、そこを卒業している。高学歴と高等教育を自明とする家庭に生まれ、そうした既定路線への抵抗や葛藤を、若き詩人はどこかで深く体験していたのかもしれない。
あるいは、鋭い錐のような感性を身に帯していた少年詩人には、彼を囲む世間というものすべてが、悪しき親密性の檻のように囲繞していて、それがひどく陳腐なものとしか感じられなかったのかもしれない。
いずれにしろ、その一、二年後に、谷川俊太郎は詩を書きはじめる。若き詩人は、そのことばは平明であるが、静かな初初しさをたたえた詩だと評価された。
とは言われたものの、その紡ぎだされたことばは、わたしには、かならずしも温室でつくられたものではなかったと見て取れる。
イングランド生まれの詩人W・H・オーデンは、詩人について「彼等は雷電のようにわれらを驚愕し、または夭折し、または長い孤独に生き延びる・・・軽騎兵のように突進し、・・・誰も振り向いてくれない者にならねばならぬ」と記している。
この激しさをくらべると、谷川俊太郎の詩にはたしかに時代と大立まわりをするような詩はすくない。だが、自伝エッセイと言うべき『ひとり暮らし』を読み進めていけば、かの詩人は、なにも闘いを避けていたわけでも、自らのことばを飼いならしていたわけでもない。たとえば「愛」ということばひとつについても、詩人はつぎのように語っている。
・・・愛とは気恥ずかしいことばです、見知らぬ外国語のような気もする。この語は私のからだにも暮らしにも、どこかまだなじんでいない。・・・だから実生活の上でも、詩を書くときも、私はいつもある意志をこめて愛という言葉を使ってきた・・・愛と呼ぶことで抽象になりかねない心身の状態が必要だったと言えばいいのか・・・。
・・・自分に生きることへの情熱が希薄ではないのかという疑いをずっともち続けています。その資質が私を人間から遠ざけ、この世の現実から遠ざけるのですが・・・。
若いころ父に「お前の詩にはドラマがない」と言われたことを思い出します。・・・情熱の希薄な私は、愛に対する憎しみという感情にも薄く、・・・それがかえって人を傷つけることもあると自覚しています。
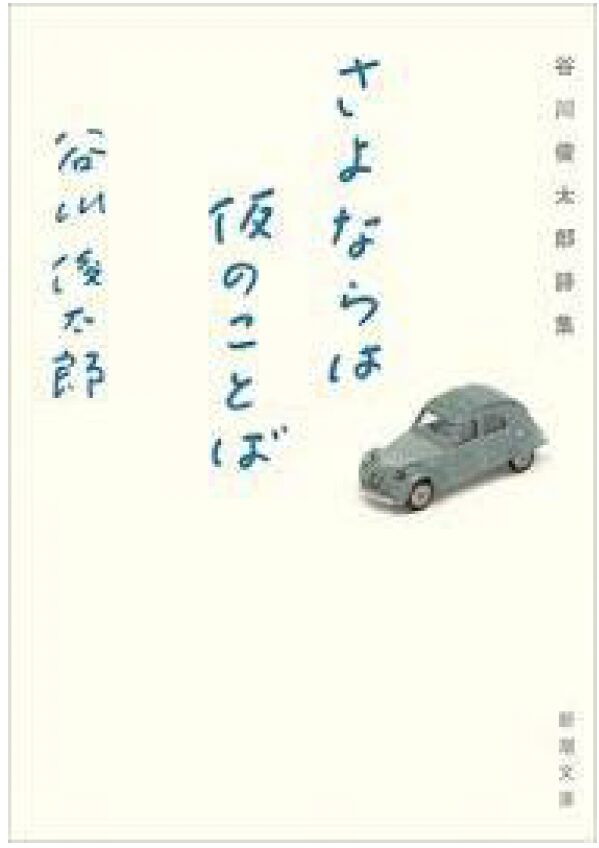
ここには行きつ戻りつする詩人の姿がある。そして詩人は、ことばを重ねる。
・・・誰がどんなにすぐれたものを書こうとも、それがどこまで人の心にとどくのか、心もとないのだ。これは一人一人の書き手の能力を超えて、時代の変化にかかわっているような気がする。
と、そんなふうに考えていくと、考えはどんどんとりとめなくなっていく。こういう考えの元になっているのは、直観みたいなものでそれには何の根拠もないからだ。だがその直観はなまじっかな理屈よりもはるかに強く自分を縛っている。それを跳ね返すほどの感情の強さ、あるいはそれに支えられた楽観がない限り、それは原因がわからない鈍痛のように人を苦しめる。
この文を読むかぎり、詩人は静かにではあるが、「私」そして「ことば」との葛藤のなかで逡巡し、苦闘している。しかもその闘いは、どこかひどく孤独で、それはまるで、なかなか内面を明かさない少年のようなありようなのである。だが、ここにひとつの澄明な光が見えてくる。
いずれにしろ、谷川俊太郎の詩は、多くの人たちに愛された。ケレンのあることばがあるわけでもなく、べつにウイットに富む詩句があるわけでもないが、ひとびとは詩人の平明さとどこかほんのりと暖かいことばに親しんだ。しかも、そのことばひとつひとつには、わかりやすいからこそ、人生の意味を感じさせる何かがあった。
三年ほど前のことであったが、とある書店で谷川俊太郎の詩と出会うことがあった。その書店は、呉清友という人物が立ち上げた書店で、台湾の台北に本拠があり、東京・室町にも支店を置いている。名を誠品書店という。
台湾は、古くから書店文化が健全に人びとの暮らしのなかに息づいているのだが、誠品書店は、その書店文化の中核的存在だと言っていい。創業者の呉清友は数年まえに亡くなったが、呉清友の言葉を集めた『誠品時光』という本が出されていて、そのなかに谷川俊太郎が呉に贈った詩が掲載されている。
わたしは、東京の誠品書店でその詩にたまたま出会った。
ページの上に言葉がある
読む者の心の中で それは事実そっくりの現実になる
だがその現実に手を触れることはできない
この現実は無痛の現実
言葉で飾り言葉で動かすことのできる現実
偽の事実という負い目を負っている
書店に置かれた本は 静かな佇まいの美しい一個の物だ
それは適正な価格で 商品として売り買いされ流通する
だが本に命を与える「言葉」は商品ではない
文字は目に見えて読むことはできるが
目に見えない魂とも呼ぶべき何かを
人から人へたおやかに本は運ぶ
短く簡潔で、ほんの軽く語りかける詩ではある。だが、これほどまでに本が伝えることばについて、やさしく、そして深くすくい取った詩があっただろうか。
谷川俊太郎の詩になぜ人びとが立ち止まるのか。それは一言で言うなら、ことばの平明さがくみ上げる砂金のような輝きを、わたしたちが愛してやまないからかもしれない。
谷川俊太郎の死を悼む。
T
