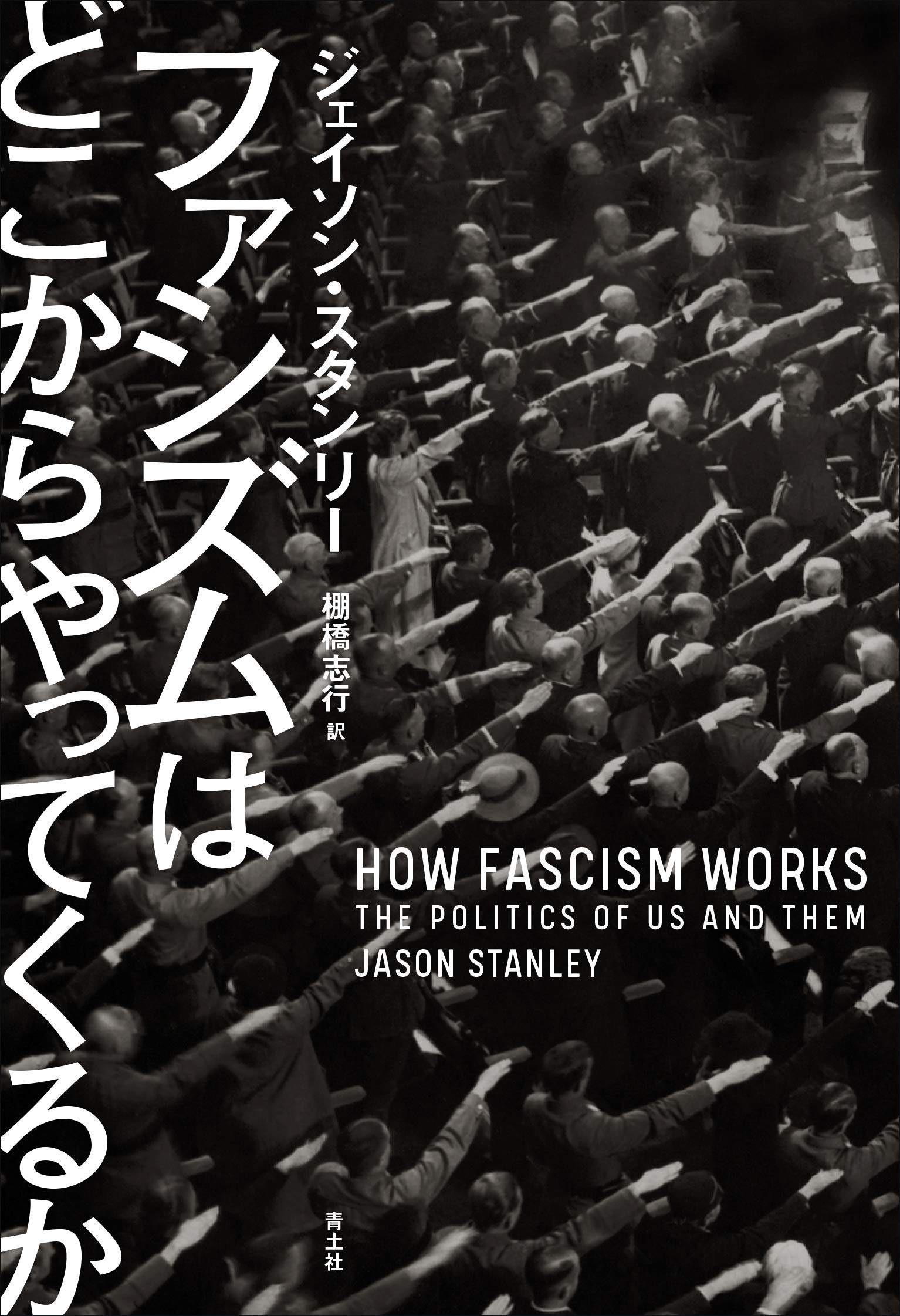
21世紀も四半世紀を過ぎて、「愚かな政治は、愚かな大衆がつくる」という政治のアフォリズム(箴言)が、世界を席巻しだしたことを思わざるをえない。
ならば、「愚かな大衆」とは何か? ということになると、だれもそのなかに自分が含まれていることを認識してはいない。
むしろ、自分はいまの世の中を賢く見極めて、〝損〟や〝失敗〟なきようにやっていると思い込んでいる者たちは多いのであろう。
はっきり言うが、問題は「現代(いま)」の利害得失、損得勘定にあるのではない。われわれがこの地球上から姿を消し、その子や孫やそのあとの人びとの世代になったとき、この地球がどうなっているか、そこにある。
戦禍にまみれる時代。人が人を平気で差別し殺戮してしまう時代。地球環境が破壊され、空気も水も土壌も汚染され、取り返しがつかなくなる時代。さらに核兵器での威嚇や乱発、原発の爆発事故で、地球が放射能で汚染され人はおろか生物も死滅してしまう時代。しかも、そんなことはおこらないと高をくくっている者たちがのさばっている時代。
「レイシズムRacism」に「ジンゴイズムJingoism」、他者を差別し等級をつけて喜んでいる大衆。自分たちさえ助かればいいというご「エゴイズムEgoism」・・・。大国主義と植民地主義、権力にすがる事大主義、権威にひれ伏す奴隷意識が地上に溢れかえる時代・・・。言うまでもなく、それらの総称には危険な情緒を身に纏う「ファシズムFascism」が覆い被さる。
そもそも、本書のタイトルにある「ファシズム」とは、20 世紀に発生した政治的用語であった。そしてその20 世紀とは、「ファシズム」国家群と「民主主義」を標榜する国家群が覇権を争い、地球上の人びとの少なくとも2 億人以上が戦火のなかで殺戮され、夥しい難民と行き場を喪った民を大量に生んだ時代。まさに「戦争の世紀」であった。
この大戦で「ファシズム枢軸Axis powers」は敗れ、スペインでのフランコ政権など一部は残存したが、「ファシズム」は唾棄すべきものとして時代からその姿を消したかのように見えた。
しかし21 世紀になると、「国民国家」という箍(タガ)が溶け始める。いわば、人権や民主主義、公共性といった「コモンセンス(共通感覚)」によって保護されていた国民が分断させられ、「国家」の意味を喪った時代が到来したのである。
振り返るなら、20 世紀という世紀は、富み栄えた赤道以北の先進諸国がアフリカや南米、そしてアジア各地の赤道以南の諸地域の地下資源と労働力への搾取が横行していた時代だった。これは「植民地主義」と呼ばれ、のちに「南北問題」とも呼ばれていく。そして、その横暴と搾取の後遺症は、21 世紀には先進諸国にツケとなって急激に現れ出す。
収奪を重ね、肌の色のちがいで差別した先進諸国は、第二次大戦後に植民地支配を脱し、自分たちだけに通用する自由と民主を掲げて、かつての被支配地の民を置き去りにした。しかし、その長年の収奪と支配は、植民地を放棄しただけでは償いきれなかった。
置き去りにされ搾取された「南」では、20 世紀半ばの大戦後に新たに台頭した列強の介入を受け、その資源をめぐっての利権争いや固陋な宗教対立や部族対立による戦乱と暴力による混乱が頻発した。それは、そこに住む住民が自由と民主の時代を生きることを絶望的に疎外していった。政争、クーデタ、独裁が交互にくりかえされ、国土は疲弊し、そこに住む人びともまた疲弊した。
さらにその混乱は、国や地域で生きる術を喪ったおびただしい人びとを出現せしめた。その結果、彼ら彼女らは同じ言語圏のかつての宗主国である、より豊かな国に殺到するようになった。大量の難民と移民が、西ヨーロッパの富裕な国々へ、そして富の象徴であったアメリカへと押し寄せてきたのである。
ただし、そうした先進国もまた、過激化した資本主義国家特有の競争社会のなかで、国内での膨大な格差を生むようになっていった。
生産至上主義、利潤至上主義の資本主義経済は、そのためにつくられた一見平等に見える教育制度とまるで工場での生産物のように人びとを均一化させるための近代学校制度の歪みの伴走を受けて、気がついてみると見事なまでの富裕と貧困の区分を実現した。そしてそれはいつしか数代にわたる連鎖を形成し、社会に格差や階級を根づかせた。
さらに利便性の魔法に縛られるようにインターネットが普及する。インターネットによる省力化は幾何級数的に社会を覆い、管理や総務や生産部分における雇用を著しく縮小させた。そのため一時は大量に存在していた「中流階級」の役どころをつぎつぎと破壊していくことになった。
しかも、そうしたSNS 空間の膨張は、いっぽうで置き去りにされていく人びとをつくり出し、金融資産を蓄積し富裕化する者を生むのとともに、地道にひたすら労働することが、ますます貧困に追い込んでしまう状況をもつくりだした。
企業化と画一的な大量生産によって、個人の営む農業は切り下げられ、小店主の利幅は抑えられ、労働者もあたかも競りにかけられたように生存権ギリギリの労賃までに平然と下げられていくのが現実となった。
かつての農村共同体はソーラーパネルの黒い帝国に、虫に食われたようにまだらの地表をあらわにし、労働組合の職場環境の改善や賃金上昇の要求は、社会の多様性とミスマッチだとされ、非正規雇用がオシャレだとする口車に乗せられ、急速に力を失っていった。そのなかで、人びとは相手を嫉妬し憎しみ、猜疑の蟻地獄に落ち、敵視するか差別するかのなかでしか、他者を自分と同じ人間だと認識できなくなる。
言うまでもなく、21 世紀のまだ四半世紀を過ぎないころから、世界はまさにいたるところに〝分断〟が居座る異様な体となった。そして世の中は「愚かな大衆の喝采」を背に、気に食わない相手を「敵」とみなし、ただただ「敵」の打倒を呼号する「ファシズム」政党がのさばりだしてくる。
本書の本タイトルは、『How Fascism Works』である。直訳すると「ファシズムのしくみ」といった意味合いである。サブ・タイトルは「The Politics of us and them」。つまり、「奴らと俺たちの政治」ということになる。言い換えるなら、それは「ファシズム」とは奴らと俺たちの〝分断〟からはじまるという意味だとしてもいい。
本書のエピローグにつぎのような一文がある。
・・・ファシスト政治は〝我々〟が主役で〝やつら〟がいない「理想化された架空の過去」を土台にし、〝我々〟が苦労して手に入れたお金を奪い取り〝我々〟の伝統を脅かす「腐敗したリベラルエリート」への憤りに支えられて、〝我々〟と〝やつら〟は別物だという神話を織り上げる。〝やつら〟は自由を与えても無駄な(自由を手にするに値しない)怠け者の犯罪者だ。〝やつら〟は自由主義や〝社会正義〟というレトリックで破壊的な目標を覆い隠し、〝我々〟の文化と伝統を破壊して〝我々〟を弱らせようと躍起になっている。〝我々〟は働き者で、法律を遵守し、労働によって自由を獲得してきた。〝やつら〟は怠け者で、性的に倒錯していて、退廃的だ。(p207)
断るまでもないが、人類の歴史に「理想化」された過去などというものはない。「理想化」を呼号する者たちの内心にあるのは、せいぜいで「現在(いま)」の汚辱にまみれた世界の裏返しにすぎない。
歴史を見るならば、人は困難に遭遇すると、手っ取り早く外からの文明や知識を導入してそれを回避しようとする。それが無理なら、安易にもうひとつのありようとして、理想化した過去の「幻影」を追い求める。こうした歴史の幻想は、麻薬のように人びとに浸潤する。
江戸時代末期に外圧が迫ったとき、「この国」では尊皇攘夷思想が跋扈するが、それは日本が〝神洲〟だったという幻想に依存したものであった。無謀で無益な戦争であった15年にもわたる「アジア太平洋戦争」で呼号された「神国日本」の幻想は、まさにそれとうり二つのものであった。
さらに「ファシズム」の温床となるものは、根拠のない被害者意識である。自分たちは苦労が報われない国にいて、財産を奪い取られ、自分たちが築いてきた文化や伝統を破壊され、怠け者で非道徳的で退廃的な〝やつら〟にやられている。よく見ていけばほとんど根拠のない情動に人びとは駆られている。
残念ながら、歴史を見ていけば〝我々〟の文化や伝統といったものは、さまざまな文化や外から入ってきたものの影響を受けて重層的に混交され形成されたものなのだ。それは遠く中東、いわばオリエントの民の信仰であったキリスト教の今日のありようを見るならば、気がつかないはずはないのである。
しかし、「やつら」と「我々」の分断をよりどころとする者たちにとって、そうした語りかけは、自分たちをペテンにかけようとする「腐敗したリベラルエリート」の詭弁だとするのである。
著者のスタンリーは、この本の冒頭で、「ファシズム」政治の10 の戦略なるものをあげている。それは、「神話的過去、政治宣伝、反知性主義(高等教育への攻撃)、非現実性(陰謀説)、階層構造(ヒーラルキー)、被害者意識、法と秩序、性的不安、ハートランド(保守的で伝統的な価値観が支配的な地域)への回帰、社会福祉と団結の解体だという。
数年前に流行ったものに、アメリカの「ホロコースト記念館」にある「ファシズムの初期兆候」を列挙したものがある。そこには、「強情なナショナリズム、人権の軽視、団結のための敵国づくり、軍事の優先、性差別の横行、マスメディアのコントロール、国家の治安に対する執着、宗教と政治の癒着、企業の保護、労働者の抑圧、学問と芸術の軽視、犯罪の厳罰化への執着、身びいきの横行と腐敗、不正な選挙」が掲げられていた。
双方比べてみてもわかるように、そこには、「やつら」と「我々」の〝分断〟が仕込まれているのであり、そのなかで「知性」への蔑視、自分たち以外の権利や自由の獲得を許さない傲慢さ、そして猛烈な被害者意識とそれを支える情緒があるのだ。もちろんその「やつら」には、弱者も外国人も含んでのことである。
それをさらに分析すると、こうした思想に吹き寄せられる人びとは、自分たちはいまの位置から「1 ミリ」も動きたくないということでもあるのだ。爛熟した資本主義の猛威により社会構造が変わり、人びとの付き合い方も、その生き方のありさまもさまざまな環境変化が起こっているのに、「ファシズム」に感応する者たちは、それはすべて誰かが悪いのであり、「インテリ」らによる策略なのであるという固陋にしがみついているのだ。
「我々」は、「1 ミリ」も動きたくない。ここからほかの場所を見よというのは、みんなペテン師だ。
そうなると当然、「我々」は、世の中の変化に想像力を働かそうとしない。想像力とは、それはすべて誰かが仕組んだ「陰謀」だとの恐怖や不安に取って代わられる。しかし、こうした「陰謀」への恐怖も、「理想化された過去」以上に自ら動こうとしない者の退嬰的な妄想でしかない。妄想はときとして麻薬のように人を覚醒させてくれる。すべての恐怖と批判はここから生まれる。
本書は、そうした「ファシズム」のいまのありようをさまざまな視座から分析したものである。ただし、「ファシズム」をどう乗り越えるかについては、さほどの説明を施していない。まずは「ファシズム」という「敵」をいかに分析して、その罠に陥らないように自戒する一書として存在しているのである。
とは言うものの、まさにいま世界は、「ファシズム」もどきの米トランプ政権が強権を発動しベネズエラ大統領を捕縛し、同じように中国・習近平やロシア・プーチンが軍の活動を活発化させ、「覇権」を全面に押し出す時代となっているのであって、そのなかで21世紀の「ファシズム」といかに対峙するかは、かなり重要な問題であるはずである。
そのためには、すくなくともまずは「ファシズム」に抗する活発な「知性」を磨くことである。つぎには自分以外の他者、それはいま会うことのできない「未来」の人びとも含め、どうすればこの地球を手渡しできるかを考えること。そして最後には、情緒的な同調を避け、自らの話が相手に理解されて初めて自己自身を理解するのと同じように、「論理」の扉を閉じられた閉域に置くのではなく、つねに開放しておくことにあるだろう。
その意味で、本書は「孤立しない論理」の扉を開くべく企図された、反「ファシズム」分析の卓越した一書と言える。
T
