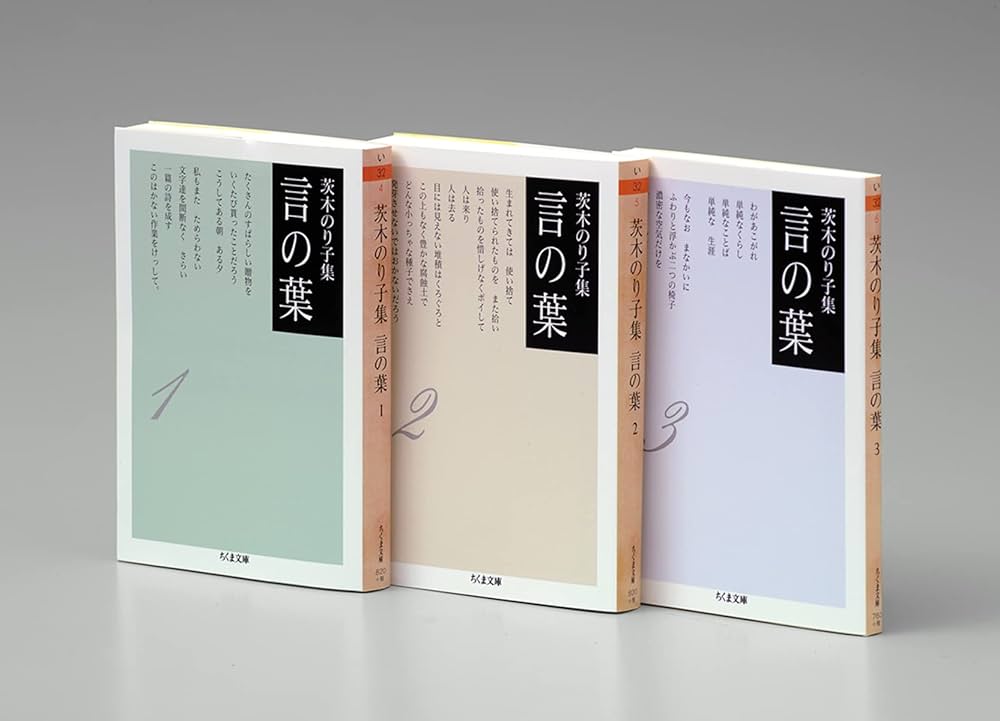
十代から二十代にかけて、詩はいつも身近なものであったように思う。なぜなら、このころ、ひとは言葉に恋する時分なのだからだ。
言葉は、散文や詩など文字に表されたものだけではない。会話で交わされる言葉。ニューポップのメロディーやラップのリズムに共振する言葉。ふと口ずさむ哀しくも切ない歌詞。これらは年ごろの若者たちの感性に響いて心のなかへ浸潤する。
感受性にうぶな若者たちは、言葉に真実が宿ることを先天的に感じる。そして、言葉の情感に自らのこころのありかを探そうとするのである。
そして、言葉は、自分の気持ちを表現するためだけのものではなく、論理も情感もすべてを含みこむ言葉は、ひとをして他者の存在を意識させ、見たことのない世界を知らしめていくものであることを知る。
しかし、いま言葉に恋する若者は、すくなくなっているのかもしれない。
茨木のり子は、日本が暗い戦争をしていた時代に高等女学校に通う少女だった。愚かな戦争がけっきょく負け戦だったと知った19 歳であったころ、彼女は薬学を学ぶ女子大生になっていた。
戦争中、彼女らは学業そっちのけで勤労動員にかり出され、精神だけがのさばる強圧的で単調な号令に取り囲まれていた。そのため、言葉に恋する青春時代を喪い、人生への眼差しは、きわめて限られたものにさせられていた。
そんな詩人は、戦後になって二十代の最後の年に、のちにはよく読まれるようになった一編の詩を書く。『わたしが一番きれいだったとき』である。
わたしが一番きれいだったとき
街々はがらがら崩れていって
とんでもないところから
青空なんかが見えたりした
わたしが一番きれいだったとき
まわりの人達が沢山死んだ
工場で 海で 名もない島で
わたしはおしゃれのきっかけを落としてしまった
わたしが一番きれいだったとき
だれもやさしい贈物を捧げてはくれなかった
男たちは挙手の礼しか知らなくて
きれいな眼差だけを残し皆発っていった
わたしが一番きれいだったとき
わたしの頭はからっぽで
わたしの心はかたくなで
手足ばかりが栗色に光った
わたしが一番きれいだったとき
わたしの国は戦争で負けた
そんな馬鹿なことってあるものか
ブラウスの腕をまくり卑屈な町をのし歩いた
わたしが一番きれいだったとき
ラジオからはジャズが溢れた
禁煙を破ったときのようにくらくらしながら
わたしは異国の甘い音楽をむさぼった
わたしが一番きれいだったとき
わたしはとてもふしあわせ
わたしはとてもとんちんかん
わたしはめっぽうさびしかった
だから決めた できれば長生きすることに
年とってから凄く美しい絵を描いた
フランスのルオー爺さんのように
ね

<若き日の茨木のり子>
・・・ね。茨木のり子の詩には、少女らしい茶目っ気と、嫌いなことは嫌いと言い切るわがままさ、そして、ある批評家が〝清冽〟と評した、すがすがしさがある(後藤正治『清冽』中央公論社2010年)。
だが、いつの時代でも、ひとは自分の生きたその時代しか生きられない。茨木のり子はその意味で戦争の時代に生きた詩人であった。だから、彼女の詩のモティーフは、おおかたつつましい恋の歌や「洗濯ものを万国旗のようにかかげる」暮らしのなかの詩だったりするのだが、そうした詩の構えのなかに、突如としていがらっぽい戦争の影が顔を出してくる。
・・・いまなお<私>を生きることのない この国の若者のひとつの顔が そこに 火を
はらんだまま凍っている
・・・地の上にも国籍不明の郵便局があって 見えない配達夫がとても律儀に走っている
かれらは伝える ひとびとへ 逝きやすい時代のこころを
・・・世界に別れを告げる日に ひとは一生をふりかえって じぶんが本当に生きた日が
あまりにすくなかったことに驚くだろう
・・・その町の人たちは気づかないけれど はじめてやってきたわたしにはよく見える
なぜって あれは その町に生れ その町に育ち けれど 遠くで死ななければな
らなかった者たちの 魂なのだ
・・・この国では つつましく せいいっぱいに生きている人々に 心のはずみを与えな
い みずからに発破をかけ たまさかゆらぐそれすらも 自滅させ 他滅させ 脅
迫するものが在る
・・・戦争責任を問われてその人は言った
そういう言葉のアヤについて 文学方面はあまり研究していないので
お答えできかねます
思わず笑いが込みあげて どす黒い笑いは吐血のように 噴きあげては 止り ま
た噴きあげる
・・・
いまなお<私>を生きることのない この国の若者のひとつの顔が そこに 火をはらんだまま凍っている
・・・
地の上にも国籍不明の郵便局があって 見えない配達夫がとても律儀に走っている かれらは伝える ひとびとへ 逝きやすい時代のこころを
・・・
世界に別れを告げる日に ひとは一生をふりかえって じぶんが本当に生きた日が あまりにすくなかったことに驚くだろう
・・・
その町の人たちは気づかないけれど はじめてやってきたわたしにはよく見える なぜって あれは その町に生れ その町に育ち けれど 遠くで死ななければな らなかった者たちの 魂なのだ
・・・
この国では つつましく せいいっぱいに生きている人々に 心のはずみを与えない みずからに発破をかけ たまさかゆらぐそれすらも 自滅させ 他滅させ 脅迫するものが在る
・・・
戦争責任を問われてその人は言った
そういう言葉のアヤについて
文学方面はあまり研究していないので
お答えできかねます
思わず笑いが込みあげて どす黒い笑いは吐血のように 噴きあげては 止り また噴きあげる
これらの言葉には、愚劣な戦争で青春を略奪されたものへの哀切と痛切がにじんでいる。そしてそれは、日常にあっても、ときとして顔を出し、その怒りは、逡巡し、内向して噴出するときもある。『自分の感受性くらい』という詩がある。
ぱさぱさに乾いてゆく心を
ひとのせいにはするな
みずから水やりを怠っておいて
気難かしくなってきたのを
友人のせいにはするな
しなやかさを失ったのはどちらなのか
苛立つのを
近親のせいにはするな
なにもかも下手だったのはわたくし
初心消えかかるのを
暮らしのせいにはするな
そもそもがひよわな志にすぎなかった
駄目なことの一切を
時代のせいにはするな
わずかに光る尊厳の放棄
自分の感受性くらい
自分で守れ
ばかものよ
ここで向けられている怒りは、自らに発せられているだけではない。自らを囲繞するそのいじけた属性におよんでいる。人に任せ、時流に惑溺して、泣き言を漏らし被害者であることを演出する狡猾さ。そもそも事物への感受性すら持ち合わせていない不感症的隣人。そうしたすべての捉えどころのない空虚なものへの怒りが、「ばかものよ」としてここに噴出する。
そして、いわば戦争という化け物も、こうした得体の知れない空気爆弾みたいなものなのであった。日本人は、そうした得体の知れない精神や細々(こまごま)とひとを縛る節義に癒着して、自らの暮らしをやり過ごしてきたのだ。
そうした時代にながく生きてきて、詩人はひとつの決断を宣言する。
もはや
できあいの思想には倚りかかりたくない
もはや
できあいの宗教には倚りかかりたくない
もはや
できあいの学問には倚りかかりたくない
もはや
いかなる権威にも倚りかかりたくない
ながく生きて
心底学んだのはそれくらい
じぶんの耳目
じぶんの二本足のみで立っていて
なに不都合のことやある
倚りかかるとすれば
椅子の背もたれだけ
詩集『倚りかからず』が刊行されたのは、茨木のり子が73 歳となった1999 年10 月のことだった。この年の前年から、東京の都心には多くホームレスが出現し、言葉を失った「キレる」若者が増大してくる。日本海には北朝鮮の工作船と思わしき船舶が現れたとして、それに被さるように日米間では戦争のできる「新ガイドライン関連法」が成立し、それとともに「日の丸・君が代を国歌・国旗とする」法律が施行され、愛国だの日本精神とやらが説かれ出していく。
まごうことない新しき戦前の出現。そんな時代にあっても詩人は、言葉への恋することをあきらめてはいない。詩人は、いたずらっぽく茶目っ気たっぷりな眼差しで世の中を見据え、踏まれても貶毀されても、したたかに復活する言葉への愛を譲りわたそうとしない。
・・・言葉の脱臼 骨折 捻挫のさま
いとをかしくて
深夜 ひとりで声をたてて笑えば
われながら鬼気迫るものあり
ひやりとするのだが そんな時
もう一人の私が耳もとで囁く
「よろしい
お前にはまだ笑う能力が残っている
乏しい能力のひとつとして
いまわのきわまで保つように」
はィ 出来ますれば
山笑う
という日本語もいい
春の微笑を通りすぎ
山よ 新緑どよもして
大いに笑え!
気がつけば いつのまにか
我が膝までがわらうようになっていた
『笑う能力』(詩集『倚りかからず』から)
と、詩人は言葉を楽しげに綴る。
先の戦争の時代を兵士として生き延びた田村隆一は、戦後になって『帰途』という詩を書いた。
言葉なんかおぼえるんじゃなかった
言葉のない世界
意味が意味にならない世界に生きていたら
どんなによかったか
あなたが美しい言葉に復讐されても
そいつは ぼくとは無関係だ
きみが静かな意味に血を流したところで
そいつも無関係だ
あなたのやさしい眼のなかにある涙
きみの沈黙の舌からおちてくる痛苦
ぼくたちの世界にもし言葉がなかったら
ぼくはただそれを眺めて立ち去るだろう
あなたの涙に 果実の核ほどの意味があるか
きみの一滴の血に この世界の夕暮れの
ふるえるような夕焼けのひびきがあるか
言葉なんかおぼえるんじゃなかった
日本語とほんのすこしの外国語をおぼえたおかげで
ぼくはあなたの涙のなかに立ちどまる
ぼくはきみの血のなかにたったひとりで帰ってくる
田村隆一全集(河出書房新社2010年)
ふと思うのである。言葉への求愛を忘れてしまった人間は、どこかで間違いを犯すのではないか。単色に染め上げられ、ひとを指嗾したり煽動するためのプロパガンダ、フェイクに踊り、薄汚れた笑顔をしながら猛々しくひとを断罪するNet とその場だだけやり過ごそうとする奸智に長けた言説・・・。そこに言葉への愛情はない。
言葉への愛情を失った時代に茨木のり子は少女時代を過ごした。いつまでもみずみずしい言葉、ひととひととをつなぐ言葉。戦後、彼女は言葉に恋することから詩人として歩きはじめた。2006 年2 月、茨木のり子は79 歳の生涯を終えた。
しかしその言葉の数々は、いまもひとびとの涙や血のなかへの通路を開くものとして、いつまでも残されている。ひとは消えても言葉は残る、と茨木のり子はきっと微笑んでいる。
R
