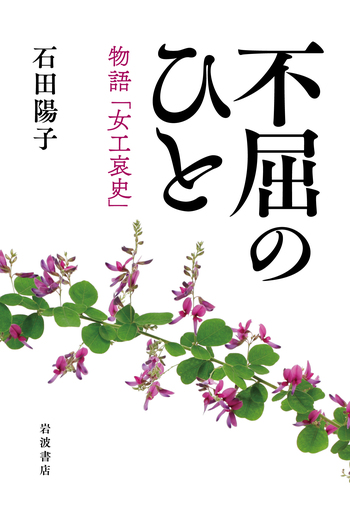
「搾取」という言葉を人びとが口にしなくなって、長い時間がたった。それに代わって現れた言葉は「格差」であったような気がする。
しかし、「搾取」と「格差」では、その現実にはおおきな隔たりがある。「搾取」とは、いうまでもなく資本家から働く者が肉体を酷使され、その命さえむしり取られ、時間を奪われ、貧困に貶められることをいう。だが、「格差」にはそうした激しさはない。むしろ生態観測をなぞったような言葉でしかない。
はたして、いまの時代に「搾取」は遠い時代の言葉なのか。本書のテーマは、その「問い」にあると言っていい。
『女工哀史』を著した細井和喜蔵が織物職工だったことはよく知られている。しかし、その生涯は短く38 年であった。そのため生前の和喜蔵の私生活はさほど知られていない。それ以上に、和喜蔵に妻がいたこともさほど知られた事実ではない。
本書は、その和喜蔵の妻であった「トシヲ」の生涯を描いたものであり、むしろ「トシヲ」の生き方を通して、大正期から昭和期の戦前と戦後を通し絵のように描ききった一書であると言っていい。
「トシヲ」の名字は堀であったそうだ。岐阜の揖斐郡久瀬村の貧農に生まれた「トシヲ」は、満十歳と5 ヶ月で故郷から30 キロも離れた大垣の織物工場の女工として働きに出されている。大正3 年というから、1914 年の世界大戦が始まったときのことである。「トシヲ」は小学校を3 ヶ月しか行っていない。
大戦中の好景気のなか、最初に働きに出た織物工場は、昼夜ぶっ通しの労働をこうした年端もいかぬ子どもに負わせた。そんなある日、「トシヲ」は作業中何度も睡魔に襲われ一瞬意識を失ったとき、回転する歯車に右手首を剪まれ大怪我を負う。血がポタポタ足下に滴っているなか、作業場にいた監督は飛んできて、「トシヲ」の耳に口を近づけ大声で「コラッ。まったく鈍臭いヤツやなおまえはツ・・・」と怒鳴りつける。あやうく骨をえぐられ手のひらがなくなるところだったのだが・・・。
怪我の手当てをして工場に戻ると、監督は「大馬鹿ものツ。おまえのせいで会社にえらい損をさせてもうたわ」と毒づく。先輩女工の頭も「顔も見とうない。もう寄宿舎に帰れツ」と言い放つ。
同じような経験は和喜蔵にもあった。故障が起きた機織り台を直そうと、歯車と歯車の間に手を入れて作業しているとき、休息から帰った組長が動力用ベルトを操作し、突然機械が回り、和喜蔵の小指が機械に挟み込まれた。「ぼんやりさらすな! このクソ坊主!」と組長の罵声が飛び、和喜蔵は殴りつけられた。
人間のありようをとことん貶める社会。こうした現実は、この時代、数限りなくおこっていた。足を骨折したまま放置され一生曲がったままの足となった炭鉱夫、指をなくした織物女工、目を潰してしまった製糸女工、湿気と寒さ、不衛生で劣悪な寄宿舎暮らしで胸を病む女工たち、腹を満たしえない粗末な食事、そのなかで低賃金で長時間の労働に追い立てられる労働者。それが「トシヲ」らが生きたいまから百年ほど前の現実だった。
そうした辛苦のなかで和喜蔵は文字を覚え、それを自由に綴る術を身につける。それは「トシヲ」も同じだった。「トシヲ」は、父が持って帰る古新聞を教科書代わりにして文字を習得する。当時の新聞には漢字の横にすべて読み仮名がふってあった。
そして「トシヲ」は運良く労働環境の整備された豊田紡機の女工になれたことで、時間に追われながらも有島武郎の『或る女』などを読み、感性や抒情を養うこともできた。
そんな二人が労働組合の運動家の紹介で出会う。そしていつしか一緒に住むようになり、「トシヲ」は和喜蔵が執筆に専念できるように、女工として、ときには女給として、その生活を支え、和喜蔵の執筆する『女工哀史』の手助けをする。
本物の女工である「トシヲ」の身体に刻み込まれた体験は、和喜蔵の『女工哀史』の幹を太くさせた。そればかりか、真実の持つ力がそこに加えられ、『女工哀史』は虐げられた労働者だけでなく、広く多くの人びとに共苦と共悲を植えつけるものとなった。
そうでなければ、『女工哀史』は、かくも長きにわたって読みづけられはしなかっただろう。まさに『女工哀史』は、和喜蔵の社会への矛盾に対する激しい怒りと「トシヲ」の体験が紡ぎ出す細部にわたる女工のリアリティが結実したものであった。
しかしこの時代の日本は、まさに災殃と狂乱のさなかにあった。関東大震災が起こる。
・・・柱がきしみ、アパートはグラグラとヨコ揺れに揺れ始めたのである。揺れはしだいに大きくなり、壁のあちこちにヒビが入り、壁土のかけらがボロボロと畳に落ちる。棚から皿、茶碗、小鉢が飛び散って割れた。和喜蔵が煎餅布団を自分たちの頭に被せたとき、今度はドーンという音とともに下から突き上げをくらって一瞬身体が浮いた。と、思ったら真下に突き落とされる。強烈な上下動に襲われた。不気味な静寂をはさんだあと、再び激しい横揺れが始まった。・・・
(本書p66)
「トシヲ」は夢中に逃げる道すがら、「飴のようにグニャリとひしゃげた火の見やぐらの鉄骨を見た。太い柱の下敷きになって眼球が飛び出した男の顔」を見る。まさに、紅蓮の炎をかいくぐるように、地獄絵図さながらの災殃のなかを逃げまどう。
しかし、地獄はこれでは留まらなかった。戒厳令下での朝鮮人への阿鼻叫喚の殺戮が始まるのである。
亀戸駅に到着したのは剣付き鉄砲を肩にして闊歩するピカピカの軍隊だ。超満員の機関車に混じっている朝鮮人を次々とひきずり下ろしていく様は、圧搾されていた乗客の我慢と苛立ち、そして鬱憤を解き放った。「朝鮮人を皆殺しにしろ!」
(本書p101)
この錯綜した場面での作者の石田陽子の筆致は怖ろしいほどのリアリティがある。いかにして震災の混乱のなかデマが飛び回り伝染していくか。それを巧みに体験者の証言を引用をなしながら、事実として浮かび上がらせている。
ただし、この朝鮮人虐殺の実態は、そもそも権力の捏造が生んだものであった。「戒厳令」は、法の建て付けとして他国との戦争および国家秩序の破壊がなければ施行されない。
このころ軍は、軍縮の世界的の気運もあり、またシベリア出兵の失敗もあり、その威信は著しく低下していた。たしかに1919 年の朝鮮「3・1 独立運動」による反日感情の拡大もあり、それに対しての恐怖は深く権力側にあったものの、事実として日本にいる朝鮮人が暴動などを起こした事実はない。
つまり、朝鮮人虐殺のいきさつは、軍の威信、威力を知らしめるため、朝鮮人が暴動を起こしたという偽情報をばら撒き、それを梃子に遮二無二「戒厳令」の発出をはかり、行われたものである。もちろん、朝鮮人暴動説に調子を合わせた代議士もいた。庶民も、多くその噂に引っ張られていった。
しかし首都圏の新聞メディアが不能に陥っているなか、こうした情報を散布できるのは震災下に唯一無線回線を使って連絡を取りえた軍であり、警察ではなかったか。加えて当時すでに各地に網を張っていた在郷軍人会の口コミのデマでしかなかったはずである。「戒厳令」の発出は、震災の混乱に乗じて功を欲望する軍の不穏な意図によると言っていい。
さらにこの震災の混乱のなか、和喜蔵や「トシヲ」の同士である川合義虎が亀戸警察署で虐殺されている。川合は、情も実も備えた指導者であった。
本書の作者石田陽子は、歴史家半藤一利と長く一緒に仕事をしてきた作家だという。その川合義虎と半藤一利との時代を超えた、いわば「歴史の結び目」を、震災のさなかの心温まる一場面として、石田はさらりと文章に溶け込ませている。
『女工哀史』を書き上げた細井和喜蔵は、大正14 年1925 年8 月16 日に没した。和喜蔵没後、『女工哀史』は社会に衝撃をもたらし、ベストセラーとなり版を重ねていく。
だが、「トシヲ」はそのときまで和喜蔵の父の反対があり、入籍していなかったのである。そのため彼女は、『女工哀史』の印税を受け取る権利を失ってしまう。さらに、そのとき「トシヲ」は和喜蔵との間になした嬰児を喪う悲劇にも遭うのである。まさに天涯孤独のまま「トシヲ」は世間にほうり出される。しかも、細井和喜蔵の妻であったことが災いをなし、どこで働こうにも雇い先からは拒絶される。
そんななか、「トシヲ」の心に灯火をともしたのが、和喜蔵を同士とも師ともする渋谷定輔からの手紙であり、貧困のなか渋谷自身が方々かき集めてもたらした見舞金だった。
余談だが、この箇所を読んだとき、わたしには電気が走る思いがした。じつはのちに大著である『農民哀史』を著した渋谷定輔とは、1980 年代後半に2 年間ほど「思想の科学」の同じ研究会で議論をともにした。そのとき、渋谷はよく細井和喜蔵の話をし、ぼくは『女工哀史』を書くから、君は『農民哀史』を書けと励ましてくれたと深い追憶の中から絞り出すように語っていた。本書のなかで、その渋谷の言葉が蘇ってくる。
そして、「トシヲ」の心に灯火をともしたもう一人は、そのころ労働争議で知り合った高井信太郎であった。信太郎と「トシヲ」は、まさに労働運動をともに闘っている者同士の紐帯から生まれた愛情によって結ばれていく。
ときは1930 年。昭和恐慌のとき、いま以上に使い捨ての時代。労働者はまさに塗炭の苦しみの中にあり、資本家側も自らの蓄財した財産を一円たりとも失いたくないなかで、賃金未払い、馘首、工場閉鎖、官憲の弾圧、暴力団を使っての労働者への暴行などが平然と行われた時代であった。
そのなかで、「トシヲ」は労働運動でほとんど家にいない信太郎を賃労働に出て支え、つぎからつぎと生まれる子どもを養育しながら、必死に、しかしたくましく生きる。
とは言え、この時期の「トシヲ」の身の上は、いつ果てるともしれない貧困の連続であった。しかも時代は、作家の小林多喜二が官憲により殺害され、夫の信太郎も警察に拘引され猛烈な暴行を受け、それ以降寝たきりになったりするなど、権力によるなりふり構わない弾圧が横行し、世はまさに暗黒時代へ向かう。そして、そうした時代の矛盾と歪みは、その後10 年もしないうちに日中戦争へ拡大し、ついに対米英戦争に突入していった。
その無謀な戦争のさなか、次男利之が腹膜炎で苦しみながら8歳で息を引き取った。その三日前に利之は黒飴を食べたいとねだったが、そのささやかな願いを「トシヲ」は貧困ゆえにかなえてやれなかった。
空襲は日に日に激しくなり、それに対して新聞は「あくまでも火と闘へ 辛さを越えてこそ勝利の黎明は近い」「叩き消せ跳ねる焼夷弾」などと、空虚な精神論を振りかざす。
それを石田は、「権力を持つ者たちは損切りができずにいる。敗北を認めることは権力構造の瓦解に直結する。国民に犠牲と消耗の限りを強いて、限界を超えて今なおやめられないのである」と、ときの権力層の思惑の惰弱さをすくい取る。
そんななか「トシヲ」たちの住む西宮が大空襲に襲われる。「トシヲ」ら家族はその猛火のなかをちりぢりになって逃げまどう。その途中で「トシヲ」が目にしたもの・・・。
肌をレンガ色に焼かれた死体、黒炭のようになった死体。全身を焼かれた死体は申し合わせたように胸を地面につけ、一様にそり返っていた。歩みを進めて、死体の群れに近づいてみる。髪の毛も目鼻立ちも焼け落ちて、赤黒いノッペラボウになっている顔は男か女かさえわからない。綺麗な顔のまま青い鼻血を出して死んでいる青年がいた。首のない胴体があって、胴体からもがれた腕や足が転がっていた。人間の頭が草むらの中にスイカのようにゴロリと転がっている。
(本書p242)
まさにこれは丸木位里・俊の描く「原爆の図」さながらの描写である。およそノンフィクションとは思えない怜悧、克明な筆致、人間が破壊される悲しみの情理に満ちている。
だが戦争が終わって民主憲法が発布されても「トシヲ」の労苦は続くのである。「トシヲ」は闇屋もやり、日雇いもやり、そのなかで世の差別と理不尽さに伊丹で労働運動を立ち上げ闘う姿勢を貫き通す。
本書を読み終わると、「トシヲ」の苦難と明るさを通して、つくづく人間性の解放と差別撤廃の根底にある、暗い時代を突き崩す力のありかを体感できるように思う。石田陽子はそれを「歴史の結び目」を紡ぐようにして語り記した。
いまもなお時給が1200 円に上がったなどといった愚かしい人間の値踏みが行われ、いっぽうで使い切れない富裕を誇る資本家・権力者のいる現実がある。それはあきらかに「格差」といったものではなく、人間への「搾取」の結果なされたものでしかない。その事実に目を開かせてくれる一書として、まさにこの本は存在すると言える。
T
註)なお、本書には高橋是清財政について「赤字公債の発行」と記しているが、高橋財政は、日銀の低金利政策と政府発行の小切手および公債を組み合わせ有効需要の創出をはかったもので、インフレ政策というより「リフレ」に近い。その意味で「赤字公債の発行」とするのには無理がある。
