円安、さらに、物価もリーズナブな日本に、いま、あふれかえるほどの外国人旅行者がやって来ます。
彼らは、この日本で、どんな思い出を得て、それぞれの国へ帰っていくのでしょう。
旅のあとに残るのは、有名観光スポットの記憶より、自分の心が揺さぶられた“もの”や“こと”であったりするような気がします。
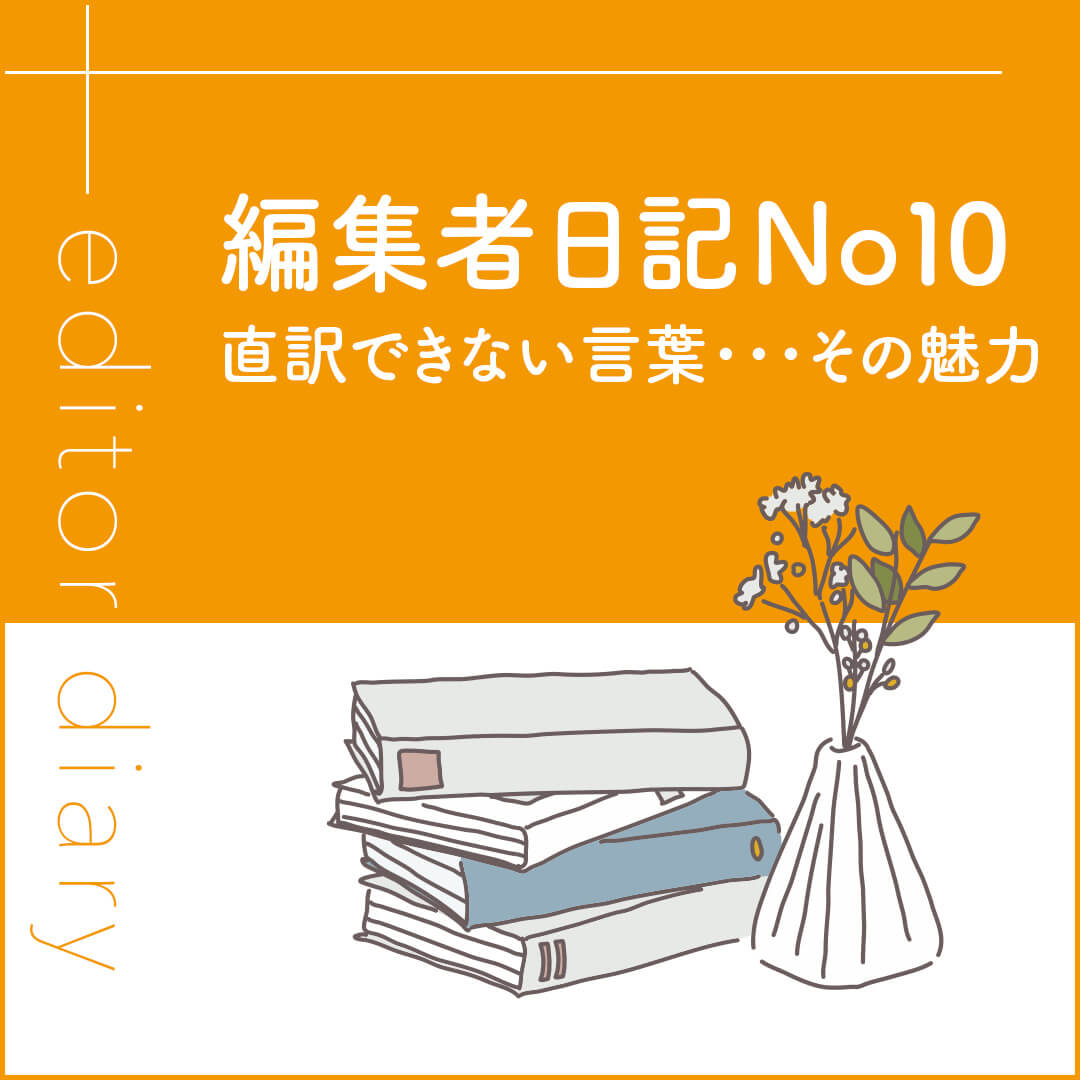
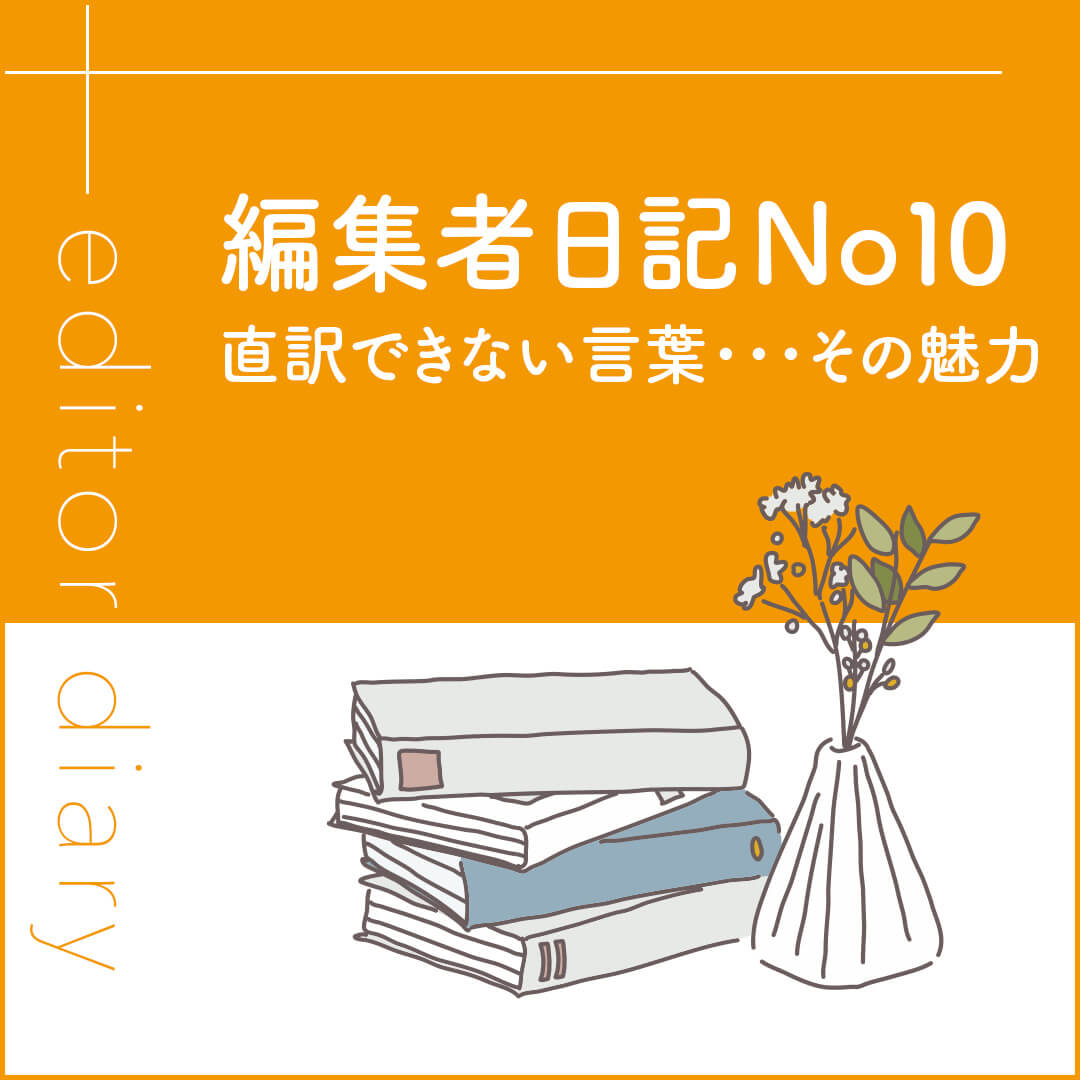
円安、さらに、物価もリーズナブな日本に、いま、あふれかえるほどの外国人旅行者がやって来ます。
彼らは、この日本で、どんな思い出を得て、それぞれの国へ帰っていくのでしょう。
旅のあとに残るのは、有名観光スポットの記憶より、自分の心が揺さぶられた“もの”や“こと”であったりするような気がします。

ガイドブックをなぞるようなあわただしい旅は好きではないので、外国に行ったときは、いつも、まずは、その街を歩いてみます。
人々の表情、話し声、街の匂い、日差しのあたりかた、影、夜の街灯、たまに出くわす路上ミュージシャン。
歩きながら、それらのものに触れ、だんだんとその国に自分が溶けていくような感覚を味わいます。

クラクフ(ポーランド)の街
何年か前にポーランドを旅しました。
アウシュビッツ収容所やシンドラーの工場など、目的も多い旅でしたが、この国にいるあいだ、いつも、ここには独特の哀愁のようなものがあると、ずっと感じ続けていました。
度重なる国土の分割、戦乱、踏みにじられた人々、そうした重い歴史を持つ国。
この国には「ジャル(ŹAL)」という言葉があるそうです。
直訳は難しく、哀愁・わびしさ・深い恨み・諦念・悲しみ・憂い・怒り・諦め・憎しみ・自己憐憫、そんなものが複雑に微妙に混ざり合った、単なる悲しみや哀愁だけでなく、儚さや壊れそうな脆さも含めた、深い感情をあらわす言葉のようです。
この独特な感情は、ポーランドの芸術や文学、音楽にも反映されていて、例えば『ショパンの手紙』にも、この「ジャル(ŹAL)」という言葉がたびたび登場し、ショパン自身も自作の“根底に流れる感情”を、「ジャル(ŹAL)」とあらわしていたようです。
ショパンのノクターン…。ポーランドの地を体感したあと、あらためて聴いてみると、日本語には直訳できないその感情が少しだけ理解できるような気がしました。

ショパン
ほかには、韓国の「恨(はん)」という言葉も、長い歴史的苦難や抑圧を背景とした独特の概念をあらわす言葉であると知ったとき、直訳できないその言葉が、強い印象とともに、しっくりと心に落ちてくるような、そんな感覚をもちました。

韓国 民画
「ジャル(ŹAL)」や「恨(はん)」とは毛色は違いますが、日本語の「わび・さび」も、外国語への直訳が難しい、日本的な表現でしょう。
「わび・さび」は、もともとは中国から伝わったようですが、日本で独自に進化し、質素、簡素、静けさ、不完全、枯れたものや古びたもの、「間」や「余白」を生かす美意識というふうな概念となっていった。
たとえば、欠けた茶碗に“美”を見出す感性…。
とてもいいですよね。
まあ、日本人が、日ごろ、それを感じて生活しているかと言えば、そうとは言えないでしょうが。(笑)

龍安寺の枯山水
直訳できない言葉を心で感じること。
人としての“豊かさ”を増やしてくれるような気がします。
外国を訪れることはもちろん、本を読むことでも、それを得ることもできる。
そんな気もします。
そして、そんな本作りがしたいものです。
